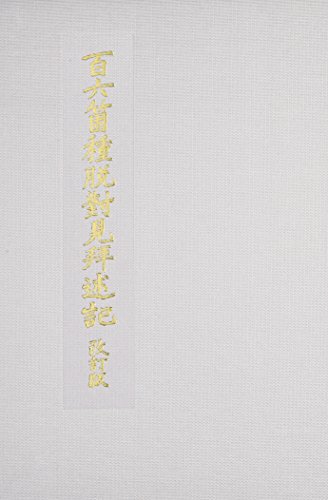1214夜:成仏をしたらその後はどうなるのか?
成仏したら末法には生まれないのか?
【質問】
成仏してしまうと、罪業がなくなって、もう末法時代には生まれてこないのでしょうか?
【回答】
たしかに、この末法という濁悪の世の中に生まれてくるのは、過去に謗法の者であった罪業によるのだ、と御書の随所に述べられています。
ところが、御書の中には、もう一つ、別なことも示されています。すなわち、「末法にして妙法蓮華経の五字を弘めん者は男女はきらふべからず、皆地涌の菩薩の出現に非ずんば唱へがたき題目なり」(御書六六六頁)
と言われているのです。
地涌の菩薩とは、法華経の会座において、日蓮大聖人が地涌の棟梁・上行菩薩として出現されていますが、その上行菩薩に従って現われた六万恒河沙という無数の眷族のことをいいます。
このことからいえば、地涌の菩薩とは御本仏日蓮大聖人様の本眷属、つまり、過去にすでに大聖人様の仏法を修行して、即身成仏を遂げたであろう人達、ということになります。
この人達が末法に生まれてきて、お題目を唱え、大聖人様の御化導のお手伝いをしているのだ、と大聖人様は言われているわけです。
このことを「願兼於業」といいます。これは、願生と業生を兼ねるということで、「願生」とは、願って生まれるということであり、「業生」とは、業によって生まれるということです。
つまり、末法濁悪の世に、悪業の果報によって生まれてきた、というのが「業生」です。
一方、「願生」というのは、末法における大聖人様の広宣流布のお手伝いをさせていただくために、また正法を護るために、大聖人様の本眷属が願って生まれてきた、ということです。
この「願生」と「業生」とを兼ねて生まれる、といいますのは、末法に地涌の菩薩の流類が生まれてくる場合は、当然、願生なのですが、末法の世の中は濁悪の世の中ですから、悪業を持った衆生でないと生まれてこられません。そこで、形どおり、罪業を作って生まれてくるのです。
すなわち、地涌の流類は過去に妙法を行じて即身成仏を遂げており、成仏の境界は自由自在ですから、もともと無かった罪業を、形どおり作って生まれてくることができる、というわけです。
仏様や菩薩が地獄に堕ちる、などということは、本来ありえないことです。しかし、菩薩が地獄の衆生を救うために、形どおり地獄の業を作って地獄の中まで行き、地獄の衆生を救うということが、小乗教の中に説かれていると、大聖人様は『開目抄』に述べられています。そして、それと同じように、作りたくない罪だけれども、形どおり罪業を作って末法に出生し、末法の衆生を救うのだ、と示されています。
したがいまして、末法には、“地涌の菩薩の流類が、願兼於業によって罪業を作って生まれてきた”というケースと、もう一つは、“本当に過去世に犯した罪業の報いによって生まれてきた”というケースの、二通りがあることになります。
では、そういう違いがどこで分かるのかといえば、これはなかなか難しい問題です。自分で「ああ、俺は業生だ」とか「あなたは願兼於業ね」とか、そんなことを勝手に断定することはできません。これは、我々凡夫の眼では、なかなか分からないのです。
ただ、経験的に一つ言えることは、入信した時からずっと見ていると、やはり、人によって正法に対する素養の違いが厳然とあるようです。
それを見ていると、やはり、仏道修行をしている人達の中に、罪業によって生まれてきた人と、願兼於業で生まれてきた人の両方がいる、ということは、認めざるえない事実であると思います。
ただし、罪業によって生まれてきて、今世で初めて妙法に縁して入信した人であっても、一生懸命に信心に励み、どんな三障四魔があっても乗り越えて、本当に正しく信心をして折伏に励んだならば、今生において地涌の流類の中に入れていただけるわけです。
逆に、願って生まれてきて、過去の約束によって信心につくことができたとしても、信心を緩くして退転ししていってしまったならば、その人は地涌の菩薩から外れてしまうでしょう。
だから、どちらにせよ、今生で一生懸命に仏道修行を貫くことが大事なのです。
ただ今の質問も、これらのことから考えればわかるだろうと思います。
すなわち、末法時代に生まれて自行化他にわたる修行をし、罪障消滅を果たして、即身成仏を遂げたとすれば、この人は地涌の流類に加えていただけます。
そして、「こんな素晴らしい人生はなかった」ということに気がついて、次の世にも、自分から願って御本尊様の元へ生まれて、「また末法広宣流布のために働かせていただこう」と、そういう人生になってくるのであります。
成仏してしまうと、罪業がなくなって、もう末法時代には生まれてこないのでしょうか?
【回答】
たしかに、この末法という濁悪の世の中に生まれてくるのは、過去に謗法の者であった罪業によるのだ、と御書の随所に述べられています。
ところが、御書の中には、もう一つ、別なことも示されています。すなわち、「末法にして妙法蓮華経の五字を弘めん者は男女はきらふべからず、皆地涌の菩薩の出現に非ずんば唱へがたき題目なり」(御書六六六頁)
と言われているのです。
地涌の菩薩とは、法華経の会座において、日蓮大聖人が地涌の棟梁・上行菩薩として出現されていますが、その上行菩薩に従って現われた六万恒河沙という無数の眷族のことをいいます。
このことからいえば、地涌の菩薩とは御本仏日蓮大聖人様の本眷属、つまり、過去にすでに大聖人様の仏法を修行して、即身成仏を遂げたであろう人達、ということになります。
この人達が末法に生まれてきて、お題目を唱え、大聖人様の御化導のお手伝いをしているのだ、と大聖人様は言われているわけです。
このことを「願兼於業」といいます。これは、願生と業生を兼ねるということで、「願生」とは、願って生まれるということであり、「業生」とは、業によって生まれるということです。
つまり、末法濁悪の世に、悪業の果報によって生まれてきた、というのが「業生」です。
一方、「願生」というのは、末法における大聖人様の広宣流布のお手伝いをさせていただくために、また正法を護るために、大聖人様の本眷属が願って生まれてきた、ということです。
この「願生」と「業生」とを兼ねて生まれる、といいますのは、末法に地涌の菩薩の流類が生まれてくる場合は、当然、願生なのですが、末法の世の中は濁悪の世の中ですから、悪業を持った衆生でないと生まれてこられません。そこで、形どおり、罪業を作って生まれてくるのです。
すなわち、地涌の流類は過去に妙法を行じて即身成仏を遂げており、成仏の境界は自由自在ですから、もともと無かった罪業を、形どおり作って生まれてくることができる、というわけです。
仏様や菩薩が地獄に堕ちる、などということは、本来ありえないことです。しかし、菩薩が地獄の衆生を救うために、形どおり地獄の業を作って地獄の中まで行き、地獄の衆生を救うということが、小乗教の中に説かれていると、大聖人様は『開目抄』に述べられています。そして、それと同じように、作りたくない罪だけれども、形どおり罪業を作って末法に出生し、末法の衆生を救うのだ、と示されています。
したがいまして、末法には、“地涌の菩薩の流類が、願兼於業によって罪業を作って生まれてきた”というケースと、もう一つは、“本当に過去世に犯した罪業の報いによって生まれてきた”というケースの、二通りがあることになります。
では、そういう違いがどこで分かるのかといえば、これはなかなか難しい問題です。自分で「ああ、俺は業生だ」とか「あなたは願兼於業ね」とか、そんなことを勝手に断定することはできません。これは、我々凡夫の眼では、なかなか分からないのです。
ただ、経験的に一つ言えることは、入信した時からずっと見ていると、やはり、人によって正法に対する素養の違いが厳然とあるようです。
それを見ていると、やはり、仏道修行をしている人達の中に、罪業によって生まれてきた人と、願兼於業で生まれてきた人の両方がいる、ということは、認めざるえない事実であると思います。
ただし、罪業によって生まれてきて、今世で初めて妙法に縁して入信した人であっても、一生懸命に信心に励み、どんな三障四魔があっても乗り越えて、本当に正しく信心をして折伏に励んだならば、今生において地涌の流類の中に入れていただけるわけです。
逆に、願って生まれてきて、過去の約束によって信心につくことができたとしても、信心を緩くして退転ししていってしまったならば、その人は地涌の菩薩から外れてしまうでしょう。
だから、どちらにせよ、今生で一生懸命に仏道修行を貫くことが大事なのです。
ただ今の質問も、これらのことから考えればわかるだろうと思います。
すなわち、末法時代に生まれて自行化他にわたる修行をし、罪障消滅を果たして、即身成仏を遂げたとすれば、この人は地涌の流類に加えていただけます。
そして、「こんな素晴らしい人生はなかった」ということに気がついて、次の世にも、自分から願って御本尊様の元へ生まれて、「また末法広宣流布のために働かせていただこう」と、そういう人生になってくるのであります。

追伸
眷属妙の話はややこしいですね。
私が御僧侶から聞いた話を少し。
ひとつは、「本未有善」「本已有善」のこと。
この時の「善」とは、釈迦仏法について善根や因縁のことで、大聖人様との御縁は別次元の話ですよと。
たしかにそうですよね。
大聖人様の御両親を始めとして、宿縁のあるであろうと推測できる方々がおられ、大聖人様の御化導を補助されています。
日興上人様や熱原法華講衆など、「本未有善」ではありえない方々がおられますものね。
あとのひとつは、「ポリ銀さんや御家族は、仏国土に生まれます。もう、娑婆世界には来ないですよ」と言われたことがあります。仏界に往生ということですね。
この辺の詳しいことは、百六箇種脱對見拜述記の眷属妙の章を御参照ください。